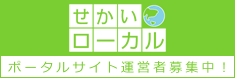- HOME
- » Whenever誌面コンテンツ
- » ヒューマンストーリー
- » 第46話 伊藤 栄俊 物語
第46話 伊藤 栄俊 物語
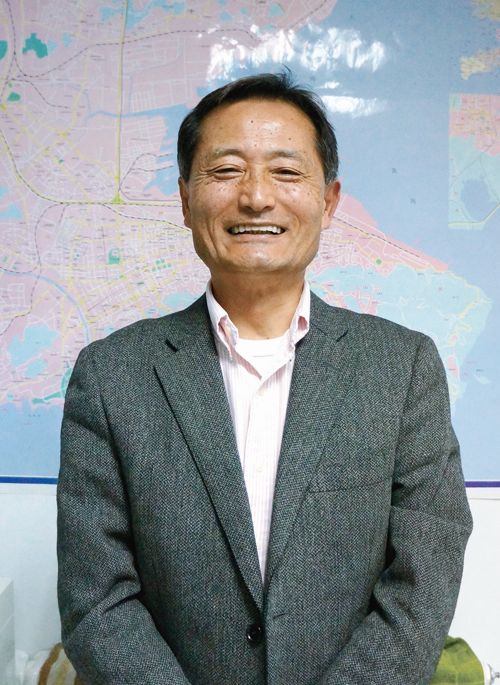



企業戦士が歩む第二の人生
中国の若者に経験を伝えたい
団塊の世代の伊藤栄俊は、企業戦士として40年近くを懸命に走り続けてきた。高度経済成長を支えてきた自負もあるが、家庭を顧みることもなかった負い目も感じている。第一線を離れたいま、大連で日本語教師として第二の人生を送り、一時帰国した時は、家族と過ごす時間を楽しみにする。
「子どもの思春期に、父親らしいことができなかった。思い出すと、悔やむ気持ちで胸が痛む。中国の若い人に自分のビジネス経験を伝えるとともに、家族への愛情も注いで、あのころを償いたい」
両親は共働きで鍵っ子世代の走り
白山連峰を遠くに望み、日本海に注ぐ手取川河口に広がる石川県旧美川町(現在の白山市)。静かで穏やかな日本の典型的な半農半漁の地域である。伊藤はこの美川町に終戦3年後の1948年(昭和23)11月に生まれた。父栄蔵は小松製作所に勤務する鋳造技術者、母八重子も繊維工場に勤める共働きの両親。一人っ子の伊藤は、鍵っ子世代の走りでもあった。
小学生のころの遊びといえば、校庭での草野球だった。日が暮れるまで近所の仲間たちと白球を追いかけた。だが、野球だけでなく、そろばん塾と書道塾にも通い続けた。奔放な面と何事にも真摯に取り組む姿勢は、同級生たちの信頼を集め、学級委員長や児童会会長を務めるなど、リーダーとしての資質を備えていた。町立美川中学校に進み、3年の時には生徒会長として、腕白たちも含めて全校をまとめたのだった。
高校は石川県内でも難関校の県立金沢泉丘高校に合格。通学は1時間15分もかかることから、3年生の1学期に学校近くの下宿に入った。夏休みが終わって2学期が始まると、担任教師に問いただされた。「お前はクラスで一番黒い。夏休みは何をしていたのか」。クラスメイトは受験勉強に打ち込み、日焼けするヒマはなかった。伊藤は、下宿の子どもを連日、市民プールへ連れて行っていたのである。そんなツケなのか、大学受験は希望した東京の国立大学に不合格となり、浪人生活が始まった。
再び同じ大学を目指したが、高校時代の担任の勧めで目標が変わった「お前には国立神戸大学の方が向いている。良い大学だから受けてみろ」。翌年には神戸大学経営学部に合格、地方育ちの伊藤は、洗練されたおしゃれな港町・神戸の雰囲気がいっぺんに気に入った。下宿生活が始まったが、卓球部に入った伊藤は練習で疲れ果て、相部屋の真面目な同級生とは生活のペースが合わなかった。間もなく別の下宿に移ったが、ここは友人の来訪や深夜の帰宅も厳禁、伊藤にとって窮屈な生活だった。2年生になって移った3軒目の下宿は天国だった。食事付きで、徹夜麻雀をやっても年老いた女性主は「お兄ちゃんたち、昨夜は頑張らはったね」と笑顔を浮かべた。
キリンビール京都工場で運命の出会い
当時は70年安保闘争が激しくなり、授業は休講が多くなって、卓球部と雀荘を往復する生活が続いた。3年生のころに学内はやっと落ち着きを取り戻し、ゼミは原価計算を選んだが、授業よりも部活動と麻雀が優先した。4年生になって東京へ会社訪問に行くと言うクラスの友人に付き合い、伊藤も大手メーカー数社を訪れた。そのひとつが京橋に本社があったキリンビールだった。面接官の質問に「父がキリンビールをいつも飲んでいたので志望しました」と答えた。だが、伊藤はキリンビールに馴染みはなかった。
そんな会話が功を奏してか、1972年(昭和47)4月に入社して京都工場の会計課に配属された。課員は8人のこぢんまりとした所帯だったが、学生時代に野球、テニス部に入っていた先輩がいて、仕事が終われば工場内の野球場や体育館に集合し、学生時代のような体育会系活動が続いた。伊藤もスポーツが大好きで、工場の人たちとコミュニケーションを深める目的もあって、テニス、卓球、バドミントンを楽しんだ。その中の1人が、製品課事務担当の登美子だった。2人は間もなく惹かれ合い、1975年(昭和50)11月にゴールインした。
その数か月後、北海道キリンレモンサービスへの出向が決まった。北海道に知人はなく、登美子は不安で一晩中泣いていた。伊藤の仕事内容は札幌市内のルートセールスだった。出向者は管理者になるのが通常だったが、ルートセールスは菓子店やパン屋、キオスクなどを回ってキリンレモンを納め、空き瓶を回収して現金精算する、営業の基本である。この下積み経験が後の栄養となるのだが、「ツルンレモンって?」「これは馬のマーク?」と言われるほど、キリンレモンの認知度は低かった。
1年後に小樽営業所長となり、登美子と2人で赴任した。あれだけ不安がっていた登美子は、ギターやテニス、スキー習うなど、すっかり北海道生活を謳歌していた。だが、伊藤は初めての管理職に戸惑っていた。組織のマネージメントや売り方がわからない、売り上げも伸びない。達成感はなく、落ち込むばかりだった。だが、翌年には業務の機械化の一環として、セールスに末端機が導入され、小樽営業所が試行営業所となったことが転機となって、心機一転のスタートを切ることができた。営業所はこれを機に一丸となり、伊藤にもリーダーとしての自覚と自信が芽生えていた。
仕事は苦労、暮らしは快適なロス駐在
1981年(昭和56)6月にキリンビール東京工場労務課へ配属となったが、伊藤にとって個人的にも思い出深い5年間の北海道勤務だった。1979年(昭和54)9月に長男裕軌、2年後の2月に次男航也が誕生したのである。3男景詩は東京工場時代の1983年(昭和58)1月に生まれ、男系の5人家族がそろった。
東京工場では人事・労務を担当し、職場の小集団で品質管理活動をするQCサークルの導入も手がけた。ここでも初めての業務にとまどったが、仕事ぶりが認められたのか、課長から今後の希望を聞かれ、伊藤はとっさに答えた。「海外に行きたい」。しかし、それは思いつきで、実現するとは思えなかった。ところが、その願いが認められ、1987年(昭和62)6月、海外ビール事業部ロサンゼルス駐在となり、キリンUSA副社長兼務で米国西部地区の営業を担当した。3か月後には登美子と子ども3人が合流、ガレージや芝生の庭付きの大きな一軒家での快適な暮らしが始まった。
しかし、仕事はここでも苦労の連続だった。部下たちは留学経験もあって、語学は堪能だが、伊藤は当初、日々の生活さえ困るほどだった。さらには、日系ライバル会社の新製品が爆発的な大ブームとなり、苦戦を強いられたのである。3年後には米国勤務を終え、東京の海外ビール事業部に戻って海外事業を統括。その翌年にはビール事業本部の情報企画担当となり、販売データ管理のほか、問屋や小売店などに入出庫管理や酒税計算をシステム化する流通支援を手がけるなど、管理職として実績を上げた。
1993年(平成5)9月、キリンビール浜松支店長に任命され、家族は埼玉の自宅に置いての単身赴任生活が始まった。この後、静岡支社マーケティング部長、同支社副支社長を経て、2000年(平成12)3月にはキリンビール北海道支社長に就任。組織人として、ひとつの階段を上り詰めたのである。道内全域を統括し、得意先の営業もやった。当然、〝飲み営業〟もあり、体を張った、忙しくも充実した日々だった。
2003年(同15)3月には東京本社酒類営業本部の営業開発部長に就任、各社が火花を散らすビール販売商戦の最前線で陣頭指揮を振るった。スーパーや飲食店などの顧客に対して、売れるための商品展示方法を提案し、店舗探しやメニューづくりなどの営業支援も企画した。また、自社の営業マンにパソコンを配備して、業務の効率化、情報の共有化も手がけた。まさにキリン人生で積み上げてきた経験の集大成である。
教え子に頼られ教師として充実感
だが、ついに34年間勤めたキリンビールを退社する時がやってきた。役職が解かれる57歳を過ぎた2006年(平成18)3月で退職、たまたまキリンビールの先輩が勤務していた水産物専門商社「新日本グローバル」に迎えられた。小さな会社で様々な業務を任され、伊藤は大連をはじめ、北欧の離島や米国などへも出張して、品質管理や会計監査にも当たった。ところが、リーマンショックの直撃を受けて売り上げは激減、同社は2009年(平成21)3月、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。
その手続きに当たったのが伊藤だった。法律を調べて弁護士と連携する一方で、債務免除の交渉もやった。伊藤にとって辛い仕事だった。その年の5月、伊藤自身も退社して、サラリーマン人生に幕を閉じた。だが、健康なうちは社会に役立ちたいと思い、日本語教師として人生の再スタートを切ることを決意した。
伊藤はさいたま市のビジネス日本語教師育成講座に通って資格を取得し、修了後の研修ツアーとして大連を訪れた。講座を主宰する高見澤猛と大連外国語大学教授の陳岩が旧知の間柄だったからだ。研修ツアーでは市内4大学を訪問し、体験授業もした。伊藤の心の中は、「この地で日本語教師になりたい」との思いが高まってきた。
帰国後、登美子や息子たちにその思いを告げた。家族は中国での一人暮らしを心配しながらも、伊藤の熱意に根負けした。こうして伊藤は2010年(平成22)3月、研修ツアーで訪問した大連東軟情報学院日本語学部の教師に就任、夢を叶えたのである。伊藤が担当するのはビジネス会話。「キリンで培った経験を中国の若い人たちに伝えたい」と、教壇に立ち続ける。
日本語学部の学生は4学年で1500人。みんな純粋で目が輝いている。卒業生の中には伊藤を頼ってやって来る者もいる。「日本の大学院進学の推薦状を書いて欲しい」「仕事が終わったら、個人的に電話応対の日本語を教えて欲しい」。そんな時、伊藤は日本語教師をやって良かった、とつくづく思う。
伊藤にとって、一時帰国する夏休みと冬休みも楽しみだ。登美子と3人の息子、そして幼い孫3人――家族とのふれあいは、企業戦士時代の償いでもあり、伊藤自身のエネルギー補給源でもある。「日本に対する理解に役立つと信じて、中国の若者に自分の経験を伝え続けたい」。伊藤はこう言って、穏やかな表情を浮かべた。
コメントをどうぞ
更新日: 2013-12-05
クチコミ数: 0
- アジアン (3)
- カフェ (11)
- スイーツ (1)
- チェーン店 (26)
- フードコート (1)
- ラーメン (13)
- 中華料理 (9)
- 和食・日本料理 (35)
- 居酒屋・バー (13)
- 洋食・西洋料理 (6)
- 焼肉 (3)
- 閉店・移転・終了 (134)
- 韓国料理 (16)
- イベント (8)
- エステ・マッサージ (3)
- カラオケ (3)
- クラブ・ディスコ (2)
- サークル (8)
- ショッピング (35)
- ハイキング (2)
- フィットネスクラブ・スポーツ (7)
- プレイスポット (4)
- 学校・スクール (12)
- 広場・公園 (13)
- 旅行 (15)
- 温泉・スパ (1)
- 観光 (52)
- 閉店・移転・終了 (95)
- 3つ星ホテル以下 (11)
- 4つ星ホテル (14)
- 5つ星ホテル (10)
- ホテル・アパートメント (38)
- マンション・オフィス (37)
- 不動産 (6)
- 乗り物 (7)
- 大連お役立ち情報 (14)
- 生活用品 (7)
- 病院・クリニック (13)
- 閉店・移転・終了 (12)
- 飲料・食品 (8)
- okaさんの食楽人生 (7)
- ニュース (1,118)
- ヒューマンストーリー (34)
- 中国、食のあれこれ (14)
- 巻頭インタビュー (64)
- 恵太太の季節を食す (18)
- 管理栄養士の食コラム (18)
- 旅順 (36)
- 開発区 (30)
- 人民路・港湾広場 (20)
- 森ビル周辺 (18)
- 中山広場周辺 (17)
- 会展中心・星海広場 (17)
- 青泥窪橋 (16)
- 民主広場・経典生活 (14)
- 友好広場 (13)
- 西安路 (10)
- ソフトウェアパーク (9)
- 和平広場 (9)
- 黒石礁 (8)
- 大連駅周辺 (7)
- ハイテクパーク (7)
- オリンピック広場 (7)
- 二七広場 (5)
- 大連空港 (4)
- 三八広場 (3)
- 馬欄広場 (2)
- 保税区 (2)
- 解放路 (1)
- 金石灘 (1)
- 華楽広場 (1)