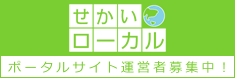- HOME
- » Whenever誌面コンテンツ
- » ヒューマンストーリー
- » 第23話 若山 昇 物語
第23話 若山 昇 物語

中国の繊維ビジネスにかけた情熱
中国への恩返しで広がる夢
中国ビジネスに携わって今年で35年を迎えた若山昇。繊維の街の岐阜市で生まれ育ち、これまで一貫して繊維にかかわって生きてきた。中国ではだまされて事業に失敗したこともあったが、パートナーとして支えてくれた生涯の友もできた。決してこの国に失望はしていない。いまあるのは中国の友人がいたからこそと感謝する。
「恩返しができれば」と言う若山。永年の中国ビジネスで培った人脈と経験を生かし、中国が近い将来、困難に陥るであろう都市問題を解決できる手助けができれば、と思う。車の増加に追いつけない駐車場、高齢化が進んで深刻さを増す高齢者施設……。還暦を迎えた若山は新たな分野での取り組みに意欲を燃やし始めている。
■わんぱく坊主が陸上との出会いで成長
若山が生まれたのは1951年(昭和26)5月。朝鮮戦争の軍需景気もあって、終戦直後の混乱から社会も経済状態も明るい兆しが見え始めていたころだった。父は岐阜駅前の繊維問屋で働き、生地販売で妻と子ども5人を養っていた。若山は末っ子のわんぱく坊主。家の裏手が貨物駅になっていて、近所の子どもたちと貨物列車に飛び乗って遊んだものだった。若山のいたずらが過ぎて、小学校の教諭から何度も呼び出しを受けた母親は「学校へは絶対に行かない」と、呼び出しどころか保護者参観さえ行くことはなかった。
岐阜市立木之本小学校の5、6年生のころ、わんぱくぶりを物語るこんな出来事をしでかした。若山は成長が早く、小学6年生でいまと同じ身長170センチ。何かと目立つ存在で、教諭の厳しい視線はいつも若山に向けられていた。その時は濡れ衣を着せられ叱られた。「何もやっていないのに!」。腹立たしさをぶつけたのは廊下の窓ガラスだった。ことごとく割ったのである。お仕置きは校長室での長い説教だった。
中学校は地元の岐阜市立本庄中学校へ進んだが、「どれほどのやんちゃ坊主が入って来るのか」と教諭たちも戦々恐々としていたという。ところが中学校ではがらりと変わった。陸上が無軌道な若山を秩序と努力という枠に収め込んだのである。
入学当初は野球部に入っていたが、球拾いばかりで面白くはなかった。そんな時に校内体育大会が開かれ、若山は100メートル走で第2位に輝いた。本庄中は陸上が強かったが、3位以下の陸上部員を抑えて上位入賞。すぐに陸上部の担当教諭から入部の誘いがあり、転部したのである。この担当教諭がすごかった。3日も練習をさぼると砂場に呼ばれ、足蹴りで倒され、ボコボコに殴られた。いまでは許されない体罰だが、若山は体で秩序を叩き込まれた。
2年生の時には生徒会役員にも立候補し、陸上部でも副主将を務め、3年生では主将にもなった。普段は勉強していなかったが、高校受験前の3か月は「これほど勉強したことはなかった」と言うほどの猛勉強。こうして進学校の名門でありながら陸上の強豪校でもある岐阜県立長良高校に合格したのだった。
■商売と生き方の基本を教えてくれた人生の師
陸上部員は男女合わせて160人。若山は1500メートルを主力にした長距離選手として実力を発揮、2、3年生の先輩を差し置いて地区大会や東海大会に出場した。若山には忘れられない大会がある。3年生で出場した全国陸上大会の県予選。社会人と一緒の3000メートル障害に出たが、水壕で社会人選手に押されて転倒、足を踏みつけられて負傷。しばらく歩行困難の状態が続いた。若山は陸上の長距離は「格闘技だ」と言う。
秋の全国駅伝大会県予選にも足の痛みをこらえて出場。3区を走った若山は16位で手渡されたたすきを5位でつないだ。豪快な11人のごぼう抜きだったが、足の痛みを抱えての踏ん張りだった。そんな若山にいくつかの大学からオファーが来た。しかし、足を痛めて競技生活をこれ以上、送れないことを若山本人が自覚していた。父1人が支えていた家計も苦しかったこともあり、大学進学を諦め、父が勧めるままに父が勤める布地会社「加藤株式会社」に就職。ここから若山の繊維人生が始った。
若山は住み込みの丁稚奉公。社長の加藤博は商売だけでなく、生き方の基本を叩き込んだ。皿洗いから掃除、洗濯……「これができない人間は下の気持ちがわからない」と説いた。加藤を人生の師と仰ぎ、この基本はいまの会社経営、社員教育にも生かされている。
当時の会社の年商は2億円ほどだったが、若山は2年後には生地販売でトップになり、会社の業績に貢献した。年功序列を排した加藤は若山に倍々ゲームで給料を上げた。実力主義の加藤の期待に応えて若山はバリバリと仕事をした。もちろん柳ケ瀬で飲み歩き、ボーナスはすべて飲み屋の借金で消えるほどの豪快で破天荒な生活を送っていた。
若山が22歳の時に3歳下の博江と結婚。この結婚は親同士が決めた〝取り引き結婚〟だった。若山の兄は博江の姉と結婚、その代わり若山は養子となった。旧姓の吉村から若山の姓に変わったのである。若山にはこだわりはなかった。「当時は交友関係が広がっていたので、整理するにはちょうどいいタイミングだった」。若山はこう言って苦笑いを浮かべた。
■国交正常化後の広州で中国ビジネススタート
結婚間もない1976年(昭和51)に人生の転機が訪れた。中国の広州交易会へ買い付けに行こうとしていた知人が、都合が悪くて行けなくなり、「お前が行かないか」と持ちかけてきた。それまで中国とはまったく無縁の世界にどっぷり浸かっていた若山。しかし、国交回復から4年が経ち、若山も中国に興味を抱き始めた。社長の加藤に相談したところ、「行って来い」と二つ返事だった。後から分かったことだが、加藤は生地販売だけの商売に限界を感じ、製造、販売への進出を考えていたのだった。
若山は香港から深圳に入り、徒歩で渡った橋の両側に紅衛兵が機関銃を手にして1メートル置きに立つ光景に「未知の中国に足を踏み入れたんだ」との思いを強くした。こうして広州入りしたのはその年の10月13日。毛沢東が亡くなってから1か月が過ぎていた。交易会場の大きさに度肝を抜かれ、中国の人の多さに驚いた。街を歩けば外国人が珍しがる中国人がぞろぞろとついてきたほどだった。
交易会ではコールテンパンツ1万本の契約を結び、1年後には製品が日本に届いた。納品までの時間はかかったが、価格の安さで儲かった。しかし、次の年の春の交易会で買った5万本のショートパンツは2年がかりでやっとさばき、損を出してしまった。社長の加藤はこう言った。「なぜだか分かるか。お前が生地と製品の二股をかけたから失敗した。生地はやめて中国からの製品輸入に徹しろ」。当時、岐阜では直接貿易をしている繊維会社はなかった。
製品の発注先は山東と江蘇、遼寧省の3工場。その経営者たちは若山のために一生懸命に応じてくれた。山東省の倪連海と江蘇省の劉健とはいまでも交友関係が続いている。しかし、大連ではだまされた苦い思いもした。地元の繊維工場経営者と合弁会社を設立、飲食業をはじめた。「うちの会社で接待に使うから絶対に儲かる」と持ちかけられ、若山個人の資金を投入したが、実際はこの会社が無銭利用して料金を踏み倒していたのだ。こうして飲食店はわずか1年で倒産してしまった。
加藤株式会社そのものも荒波に揉まれ始めていた。加藤は20年前に亡くなり、加藤の家族が経営トップとなった。当時の年商は32億円にも達し、その80パーセントを若山の中国貿易が支えていた。経営陣の交代で給料は減らされ、加藤が若山に対して支給していた「車のクラウン1台分のボーナス」もなくなった。30年近く勤めた加藤株式会社を辞めるのに戸惑いはなかった。
■恩返しで中国の社会システムの整備を
若山は岐阜の友人とともに新会社「日昇株式会社」を設立、繊維製品の検品と輸入貿易を始めた。若山が中国を舞台にビジネスを取り仕切り、友人が経理を担当した。仕事を数多くこなしているのに、なぜか赤字続き。友人が別の自分の会社の資金繰りに流用していたことが後で発覚した。中国に根付き、ビジネスに不可欠な人脈も培ってきた。「この手で中国ビジネスを成功させたい」との思いから、2006年(平成18)に同名の「日昇株式会社」を岐阜県羽島市に設立。永年の経験を武器に自分の会社を立ち上げる夢を実現させたのである。
若山の会社では「出張検品」にこだわる。コートやスーツなど〝重衣料〟は検品場に移動させるだけで型が崩れてしまう。そこで社員を製造会社に出向かせ、工場で製品をチェックするのである。しかし、社員を顧客と対面させるには、交渉力やコミュニケーション能力をつけさせなければならない。若山が社員に日本流の礼儀を教育させる理由はここにあった。こうした手法が大手衣料販売会社「AOKI」の信頼を受け、いまでは同社製品のほとんどの検品を請け負っている。
製品輸入も若山独自のノウハウがある。いまは上海と大連、西安の3工場に製造を依頼しているが、発注ユニットは少量にして、発注から納期までのサイクルを早くした。これならば互いに在庫を持たずに済み、資金繰りも楽にできる。はじめは拒否していた工場側も合理的なシステムを納得、順調な取り引きが続いている。
羽島市に本社、大連に現地法人、上海に事務所を構え、総勢200人のスタッフとともに中国で着実に基盤を築き上げる若山。この10月にはインドネシアで出張検品の拠点を立ち上げ、還暦を迎えてさらに飛躍しようとしている。しかし、最近はビジネスを超えたビジョンが心にひっかかるようになってきた。中国への恩返しである。若山はこう言って目を輝かせた。
「中国は世界第二の経済大国になった。しかし、社会システムはまだ未成熟。いずれ駐車場問題や高齢者問題で行き詰まるに違いない。政府の補助金待ちの投資構造では解決の道は遠いだろう。そこで日本の経験と技術をもって、この国が名実ともに世界の大国になれるよう、力を尽くしたい」
コメントをどうぞ
更新日: 2012-02-24
クチコミ数: 0
- アジアン (3)
- カフェ (11)
- スイーツ (1)
- チェーン店 (26)
- フードコート (1)
- ラーメン (13)
- 中華料理 (9)
- 和食・日本料理 (35)
- 居酒屋・バー (13)
- 洋食・西洋料理 (6)
- 焼肉 (3)
- 閉店・移転・終了 (134)
- 韓国料理 (16)
- イベント (8)
- エステ・マッサージ (3)
- カラオケ (3)
- クラブ・ディスコ (2)
- サークル (8)
- ショッピング (35)
- ハイキング (2)
- フィットネスクラブ・スポーツ (7)
- プレイスポット (4)
- 学校・スクール (12)
- 広場・公園 (13)
- 旅行 (15)
- 温泉・スパ (1)
- 観光 (52)
- 閉店・移転・終了 (95)
- 3つ星ホテル以下 (11)
- 4つ星ホテル (14)
- 5つ星ホテル (10)
- ホテル・アパートメント (38)
- マンション・オフィス (37)
- 不動産 (6)
- 乗り物 (7)
- 大連お役立ち情報 (14)
- 生活用品 (7)
- 病院・クリニック (13)
- 閉店・移転・終了 (12)
- 飲料・食品 (8)
- okaさんの食楽人生 (7)
- ニュース (1,118)
- ヒューマンストーリー (34)
- 中国、食のあれこれ (14)
- 巻頭インタビュー (64)
- 恵太太の季節を食す (18)
- 管理栄養士の食コラム (18)
- 旅順 (36)
- 開発区 (30)
- 人民路・港湾広場 (20)
- 森ビル周辺 (18)
- 中山広場周辺 (17)
- 会展中心・星海広場 (17)
- 青泥窪橋 (16)
- 民主広場・経典生活 (14)
- 友好広場 (13)
- 西安路 (10)
- ソフトウェアパーク (9)
- 和平広場 (9)
- 黒石礁 (8)
- 大連駅周辺 (7)
- ハイテクパーク (7)
- オリンピック広場 (7)
- 二七広場 (5)
- 大連空港 (4)
- 三八広場 (3)
- 馬欄広場 (2)
- 保税区 (2)
- 解放路 (1)
- 金石灘 (1)
- 華楽広場 (1)