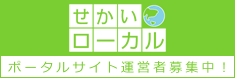- HOME
- » Whenever誌面コンテンツ
- » ヒューマンストーリー
- » 第47話 三浦 純 物語
第47話 三浦 純 物語

仲間や家族ら周囲に支えられて
しなやかに挑む物流の世界
物流会社「スキャンウェルロジスティクス大連」のリーダーとして中国人スタッフ11人を束ねる三浦純。各種貨物から引っ越し、ペットの帰国手続きまで、他地区の日本人同僚たちとも連携しながら、手際良く仕事をこなす。海外で逞しく働く女性――三浦は〝しなやかな強さ〟を持ち合わせる。
そんな三浦の周りには、いつも信頼できる仲間たちがいる。同僚や友人、そして家族。中国で生きるためのエネルギー源でもある。「仲間や家族の励ましがあったからこそ」と感謝する。三浦純、31歳。周囲の人たちに支えられながら、キャリアを着実に積み上げている。
ブラスバンド部で培った仲間との調和
三浦は1982年(昭和57)9月、京都市城東区に生まれた。しかし、1年後に一家は大阪市住之江区に転居し、幼いころの記憶はこの埋立地である南港地区に始まる。父、正晴は車のバッテリー会社の営業マン、母、佐代子は専業主婦、姉は5歳上の和子と、3歳上の真由美。正晴以外は女性ばかりで、三浦の名前は「次は男の子が欲しい」という正晴の願いが込められていたのである。
住まいは戦後の経済成長を象徴する巨大団地。周囲は無機質なコンクリートに囲まれ、3姉妹は典型的な団地っ子として育った。三浦が小学2年生の時、兵庫県明石市の郊外にマイホームを購入して移り住んだ。当時は家の回りに田んぼが広がり、三浦は初めて本物のヘビやカエルを目にした。
小学高学年ですでに身長160センチと大柄だったが、「運動オンチで大人しかった」。スポーツの代わりに、下校後は書道塾、学習塾、英会話塾に通い続けた。そこには正晴の教育方針が強く打ち出されていた。「女の子が社会進出できるためには、学力をつけなければならない」。女系家族の中で優しく控えめな正晴だが、ここぞ、という最終判断は〝家長〟の役割だった。
明石市立魚住中学校に進学した三浦は、部活動は文科系のブラスバンド部に入部した。運動部系を避けたのだが、ブラスバンド部は上下関係が厳しく、規律と結束力が求められる、準運動部だった。三浦は裏方のチューバを担当し、休みもなく練習に明け暮れた。県大会で金賞を受けるなど、県内強豪校の一角を占めるほどだった。三浦はこのブラスバンド部で、仲間との調和、助け合うことの大切さを知ったのである。
高校進学は当時、エリア内6校から受験なしで希望校を選ぶ学校選抜。三浦は最も離れた県立明石高校を選んだ。電車通学と自由な校風、可愛い制服への憧れもあった。そのころ、高校生の間で顔グロ、古着が流行し、三浦はカジュアルな古着派として、大阪ミナミのアメリカ村に通ったり、途中下車して友人と飲食したり、のびのびとした高校生活を送った。やがて進路を決める段階になって、日常生活では何も言わなかった正晴が「4年制大学へ進め」と〝家長判断〟を下した。姉2人も4年制大学と短大をそれぞれ卒業していた。
積極的な生き方を求めて中国留学
三浦は両親の経済的な負担にならないようにと、自宅通学できる神戸市の甲南女子大学を受験して合格。しかし、それまで三浦が経験したことのない別世界の大学だった。いわゆる〝お嬢様大学〟で、私学高校から上がってきた会社経営の娘たちが多く、公立高校から入った三浦はカルチャーショックを受けた。コギャル時代と言われ、ファッション雑誌「JJ」などの読者モデルとして脚光を浴びた同級生もいたし、合コンは神戸大学医学部の学生と決まっていた。
三浦は居酒屋やイタリア料理店などでアルバイトをしながら授業を受け、時には友人たちと大学近くのおしゃれな飲食店で楽しい時間を過ごしたものだった。華やかで個性的な〝お嬢様〟たちと接する中で、彼女たちも悩みを抱えていることが分かった。「大学卒業後は、家業を継がなければならなかったり、見合い結婚も決まっていたり、縛りの中で束の間の自由の女子大生活を送っていた」。三浦はそんな友人たちとは違った人生を歩むことを意識していた。
大学3年の時、神戸市と友好都市提携を結んでいた中国・天津市の大学に1か月の短期留学をした。馴染みやすそうだったから、と第二外国語で選んだのが中国語だったからである。この留学で将来、中国ビジネスにかかわることになるとは予想もしなかったが、中国のスケールの大きさ、活気ある街の姿に驚き、感銘を受けたのだ。
卒業後の就職先に選んだのは、大阪の物流会社だった。長女の和子が大阪外国語大学(現在の大阪大学)を卒業して、物流会社で働いていたことに強く影響を受けていた。「私も姉のように世界を相手に仕事をしたい」。入社した物流会社は外航船を所有する船主業で、中小企業だったが新造船も入れてダイナミックな経営をしていた。だが、三浦の仕事は営業事務。勤務時間は朝8時から夜6時までと、典型的なOLの仕事だった。「もっと主体的に働きたい」との思いが次第に募ってきた。
退社後は週2回、中国語教室に通っていたこともあって、「本格的に中国語を勉強して、話せるようになりたい」と、会社を辞めて、北京の対外経済貿易大学に1年間、留学することを決意。2007年(平成19)8月、三浦は24歳を迎えていた。社会人として仕切り直しができる最後のチャンス、と身を引き締めての中国留学だった。
失意から織戸との運命的な出会い
留学先の大学は、小規模で中国人と交流しやすい環境にあったことから決めたのだが、三浦にとって充実した留学生活となり、「中国と物流」という方向性を結びつけることになった。留学生仲間は韓国、フランス、ドイツ、カザフスタンなど多国籍で、片言の中国語で食事をしたり、カラオケに行ったり、国際的な交流を深め合うことができた。開放された環境の中でエネルギーもわき、勉強にも打ち込んで、初級から中級クラスへと進んだ。
留学生活もあと2か月を残すばかりとなった時、「1年間の留学では完全な中国語を話すことはできない。中国で働いて中国語に磨きをかけ、自分のキャリアに」と思って人材会社に求職登録。留学修了後の2008年(平成20)7月、北京の日系物流会社に就職が内定したが、北京政府の方針で北京オリンピック開催中は就業ビザ申請が全面ストップとなり、採用見送りとなってしまった。希望は失意へと変わり、将来が見えない不安感に襲われた。だが、間もなく運命的な出会いが巡ってきた。

国際的な交流をした留学生時代
人材会社を通して、スキャンウェル日本部を統括する織戸敏子の面接を受けたのだった。織戸は若い日本人の女性スタッフを何人も育て上げた敏腕リーダーである。「自分の力で切り開ける人材を求めている。一緒に頑張ろう」。織戸は、物流経験があり、中国で働く強い意欲を持つ三浦の資質を見抜き、熱心に入社を誘った。ただし、勤務地は三浦が一度も訪れたことのない大連。地方都市の勤務に躊躇したが、織戸の熱意と人柄に惚れ込んで2008年(平成20)11月、大連の地を踏んだのである。
三浦はすぐに、大連が気に入った。北京には海がないが、大連の海が見える景色に安心感を覚え、日本人にとって暮らし良さを実感した。だが、仕事には戸惑いがあった。中国人スタッフは11人で、日本人は三浦だけ。日本の会社ならば上司や先輩に判断を仰ぐことができるが、ここではすべてを自分が決定しなければならない。そんな三浦の武器になったのが、物流経験と日本企業の仕組みを知っていることだった。早口の中国語が飛び交う会社の中で、三浦は鍛えられ、仕事に手応えも次第に感じるようになっていた。
喜びと悲しみを味わった大連の5年
業務のメーンは引っ越し。日系の大手運輸会社が凌ぎを削るが、顧客が次の仕事を紹介してくれ、「頼んで良かった」との反応も多くなってきた。三浦は大連コミュニティーの優しさ、人間関係の重要性を改めて感じ取っている。個人の生活面でも人と人のつながりを大切にしてきた。1982、83年(昭和57、58)生まれのメンバーで構成する「犬豚会」は、三浦にとって気の置けないサークルだ。
三浦の前任者が同世代に呼びかけて結成し、いまは三浦が引き継いで毎月、食事会を開いている。毎回10人ほどが集まり、買い物や食事、美容などの情報を交換し、習慣や文化、勝手の違う海外で生活する上で、どれほど心強く、役立ったことか。このサークルでも仲間たちの存在に、ありがたさを痛感している。

職場の中国人スタッフと
しかし、大連では身近な人の死にも直面し、人の命のはかなさに涙した。2011年(平成23)には、兄妹のように仲良くしていた神戸の従兄弟が32歳の若さで病死し、2013年(平成25)1月には三浦が慕った寺嶋奈美子が急逝した。寺嶋は20歳以上も年上だったが、大連への引っ越し業務の依頼を受けてから、毎日のように電話で話し、週に1回は食事をして日々の出来事を語り合い、人生のアドバイスも受けた。大連の友人であり、姉であり、母でもあった寺嶋。いまでも「うんうん、そうなの」と、親身になって聞いてくれる寺嶋の笑顔を思い出す。
親しかった2人の死を通して、周囲の人たち、相手を思いやる心の優しさ、悔いの残らぬ人間関係の大切さを改めて知った。2人の思い出を胸に、三浦は「少しでも強く生きて行こう」と思う。
その原点となるのが家族だ。明石の実家には4か月に1度帰り、両親と温泉に行ったり、姉の子どもたちを含めた一家9人が勢揃いしたりして、居心地の良い時間を過ごす。この絆こそ、タフな中国で働く三浦のエネルギー源にもなっている。
周囲に励まされ、助けられながら、大連で勤務して5年余りが過ぎたが、まだ、人生の航海図は明確には描かれていない。しかし、三浦にはおぼろげながらも進むべき針路が見え始めてきた。日本と中国で物流業務に取り組み、両国の社会システムも理解できるようになった三浦。中国ビジネスのキャリアは積んできた。「もう一度、日本社会で働いてみたい。できるならば東京で」。そんな夢を抱くようになってきた。三浦の挑戦は新たなステージを引き寄せようとしているのかも知れない。

仲良しの母と3姉妹
コメントをどうぞ
更新日: 2014-01-10
クチコミ数: 0
- アジアン (3)
- カフェ (11)
- スイーツ (1)
- チェーン店 (26)
- フードコート (1)
- ラーメン (13)
- 中華料理 (9)
- 和食・日本料理 (35)
- 居酒屋・バー (13)
- 洋食・西洋料理 (6)
- 焼肉 (3)
- 閉店・移転・終了 (134)
- 韓国料理 (16)
- イベント (8)
- エステ・マッサージ (3)
- カラオケ (3)
- クラブ・ディスコ (2)
- サークル (8)
- ショッピング (35)
- ハイキング (2)
- フィットネスクラブ・スポーツ (7)
- プレイスポット (4)
- 学校・スクール (12)
- 広場・公園 (13)
- 旅行 (15)
- 温泉・スパ (1)
- 観光 (52)
- 閉店・移転・終了 (95)
- 3つ星ホテル以下 (11)
- 4つ星ホテル (14)
- 5つ星ホテル (10)
- ホテル・アパートメント (38)
- マンション・オフィス (37)
- 不動産 (6)
- 乗り物 (7)
- 大連お役立ち情報 (14)
- 生活用品 (7)
- 病院・クリニック (13)
- 閉店・移転・終了 (12)
- 飲料・食品 (8)
- okaさんの食楽人生 (7)
- ニュース (1,118)
- ヒューマンストーリー (34)
- 中国、食のあれこれ (14)
- 巻頭インタビュー (64)
- 恵太太の季節を食す (18)
- 管理栄養士の食コラム (18)
- 旅順 (36)
- 開発区 (30)
- 人民路・港湾広場 (20)
- 森ビル周辺 (18)
- 中山広場周辺 (17)
- 会展中心・星海広場 (17)
- 青泥窪橋 (16)
- 民主広場・経典生活 (14)
- 友好広場 (13)
- 西安路 (10)
- ソフトウェアパーク (9)
- 和平広場 (9)
- 黒石礁 (8)
- 大連駅周辺 (7)
- ハイテクパーク (7)
- オリンピック広場 (7)
- 二七広場 (5)
- 大連空港 (4)
- 三八広場 (3)
- 馬欄広場 (2)
- 保税区 (2)
- 解放路 (1)
- 金石灘 (1)
- 華楽広場 (1)