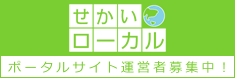- HOME
- » Whenever誌面コンテンツ
- » ヒューマンストーリー
- » 第18話 千田 清 物語
第18話 千田 清 物語

大連で見つけた新たな人生の道筋
支えてくれた人たちへ恩返し
大連で見つけた新たな人生の道筋

支えてくれた人たちへ恩返し
大連市民のエネルギーがみなぎる二七広場。その一角にある商業ビル「温州城」の4階で、各種アクセサリーや中国結、工芸品などの販売店「創作何」を経営する千田清。パートナー王静とともに中国人を相手に商売する姿は、この地に溶け込んで来た千田の人生を映し出している。
「不思議と周囲の人に恵まれ、多くの人に支えられて人生を歩んで来た。これからは支える側になりたい。そのためにも長生きして恩返しをしなければ」。千田は長年の商社マン時代の生活から、まったく違った人生をこの大連で歩み続けている。
家族の愛情と自然に育まれた幼年期
千田は1945年(昭和20)7月25日に現在の群馬県高崎市榛名湖町に生まれた。終戦のわずか3週間前である。大都市の多くは米軍の空襲を受けて焼け野原となっていたが、伊香保温泉やカルデラ湖の榛名湖、榛名富士の自然豊かな観光資源に恵まれた榛名湖町は、平和な山間地ののどかな風景に包まれていた。
両親は唐沢東一とキミ。千田は結婚して養子となったため姓を変えたが、唐沢家7人兄姉の末っ子の4男坊である。家業は榛名富士を望む旅館で、その名も「ふじや」。現在もリゾート地の旅館として千田の姪夫婦が経営している。
千田は母キミが45歳の時に生まれた子どもだった。末っ子だけに両親から愛情をいっぱい受け、兄姉からも可愛がられた。子守役はすぐ上の姉。とは言っても12歳も離れ、長姉とは親子ほどの20歳違いだった。小学校は地元の町立榛名山第四小学校。全校児童56人の複式学級で、山や川での野外授業と称した遊び時間も多かった。終戦後の食糧難でいつも腹を空かせていたが、千田は自然に恵まれた牧歌的な故郷で伸び伸びと育った。
中学校は前橋市立第3中学校に越境入学した。「兄姉が多い下の子どもたちは地元に残れない。せめて学問を身に付けさせて自立させてやりたい」。そんな父東一の親心である。寄宿先は子守り役だった姉の嫁ぎ先。先に越境入学していた2歳上の兄と一緒の生活だった。
中学生活での思い出と言えば方言でいじめられたことだ。榛名湖は語尾に特徴のある「だんべ言葉」。前橋は県庁所在地だけに標準語が混じる。からかわれ、ドッジボールでも容赦なくボールをぶつけられた。しかし、そんな学校生活にも間もなく慣れ、高校は進学校の県立前橋高校に合格した。
「2歳上の兄は優秀で、いつも兄と比較されていた。その兄は前橋高校に入学していたのでプレッシャーは大きかった。それだけに合格の喜びは大きかった」。千田はまるで昨日のことの様に笑顔でこう語る。
兄は早稲田から銀行、弟は慶応から商社
前橋高校は男子校の典型的な受験校だった。しかし、千田は中学校時代の体操部に引き続いて高校でも器械体操部の活動に打ち込み、大学受験は滑り止めもすべて落ちて一浪。兄は早稲田大学政経学部に入っていただけに落ちたショックは大きかった。
浪人時代は西武新宿線の沿線に住んでいた兄の近くに下宿。朝6時に起きて予備校に通い、昼過ぎに帰宅して自習し、夜は12時に就寝という規則正しい受験生活に徹した。その甲斐あって翌年はすべての大学に合格。「就職には早稲田より慶応の方が有利」という兄のアドバイスで慶応義塾の法学部に入学した。
大学ではボランティア団体に所属し、地域の福祉委員のサポート役として少年更正施設の慰問活動を続けた。また、3年生では三田祭実行委員として広報宣伝部に所属し、三田祭ニュースの編集を担当。この時に浅利慶太や藤山噯一郎、加藤登紀子、松原千恵子、ザ・ピーナツといった各界の著名人にインタビューし、その道に秀でた人たちの凄さも知った。
そんな大学生活も就職活動の4年生を迎えていた。兄は日本信託銀行に就職していたが、千田は銀行よりも商社に興味を抱き、6月に伊藤忠商事を受験。しかし、採用は慶応の法学部からたった1人の狭き門だったこともあり、不合格となってしまった。友人の誘いで雑誌社や旅行会社なども受けて合格した会社もあったが、やはり商社を諦めきれない。焦り始めていた8月、伊藤忠商事の子会社の伊藤忠建材から急に呼び出しを受けて面接。その後の試験に合格、商社マンとしての道が開けたのだった。
晴れて1969年(昭和44)4月に東京・日本橋の伊藤忠建材に入社。新人研修が修了し、いよいよ地方配属が決まる段階になって、「あんなに恐ろしい先輩がいるあそこだけには行きたくない」と、ふと漏らした言葉があだとなった。配属先は名古屋支店で、そこには立教大学柔道部出身の〝恐ろしい先輩〟がいたのだった。しかし、人間とは分からないもので、面倒見がすごくよくて、支店の中核的存在でもあった。
名古屋時代に学んだ商社マンの基礎
名古屋支店長の西川又一も千田にとって商社マンとしての基礎を築いてくれた恩人でもある。千田を仕事に同行させ、難しい交渉なども実践を通して教育した。このときの支店メンバーは結束が固く、3年前まで毎年、西川を囲んでの「又一会」を開いて旧交を温め合っていた。千田は名古屋支店に勤務した8年のうち4年間、西川の薫陶を受けたのだった。
この名古屋時代には人生の大きな出会いがあった。寮のおばさんが「慶応の卒業で神奈川の日吉に住んでいるので気が合うはず」と紹介してくれ、1971年(昭和46)10月に結婚した和子だった。「スカートの女性が多いのに、ズボンをはいていたのが印象的だった。楽しそうによく笑い、私にない性格を持っていた」。結婚と同時に唐沢から婿養子として千田の姓を名乗ることになった。翌年には長女三砂子、さらにその4年後には次女の里恵子が誕生、1家4人の幸せな生活だった。
名古屋から金沢に転勤となって5年間勤務したが、最後の1年間は千田にとって辛い単身生活となった。和子と2人の子どもは高齢になって来た千田の両親の面倒を見なければならず、横浜に買った自宅で両親と暮らすことになった。料理や洗濯、掃除などの身の回りのことは自分でやらなければならず、週末も休めないほど仕事に忙殺された。
「自宅の近くに転勤させて欲しい」。会社は千田の希望を受け入れ、宇都宮営業所に転勤となった。さらに4年後の1986年(昭和61)には横浜営業所勤務となり、やっと自宅通勤できるようになった。営業所は2年後に支店に昇格し、千田も合板建材課長、さらには支店長補佐も勤め、管理職への道を歩き始めた。当時はバブル経済の絶頂期。伝票が頭の上から降って来る忙しさだった。同じビルには伊藤忠商事も入居し、グループとしてのビジネス戦略を展開するなど、商社マンとして最も充実した日々だった。
横浜時代には会社全体でも先駆けとなった功績もあった。伝票管理をパソコンによるデータ管理にしようという試みで、横浜支店がそのモデルに選ばれた。本社間とのデータ共有、管理だけでなく、主要な顧客にも広げ、伝票処理のスピードは格段に上がり、ミスも激減するなど、当時としては画期的なシステムとなった。このデータ化の指揮を振ったのが千田だった。
8年間の横浜勤務に続いて1992年(平成4)に松本営業所長として長野県に赴任。長野冬季五輪が開催され、松本サリン事件も起きるなど、長野県が大きな注目を集めた時だった。2年後には東京本社へ転勤、その後、新潟勤務を経て再び東京本社に戻り、1999年(平成11)には建材商社では初めてとなった環境ISOの導入も手がけた。
孤独感に虚しさに襲われた妻の死
しかし、人生は時として残酷なシナリオを用意している。妻和子の末期ガンが発覚。2001年(平成13)8月のことだった。「退社して妻の看病をさせて欲しい」。会社の了解を取り付け、間もなく早期退職できる、と言う矢先に和子は逝った。享年56歳、千田は定年まで2年を残していた。
和子は自分の両親の看病を続け、2人を見送り届け、これから自分の人生が始まろうとしていた。千田はそれを思うと残念でならない。心にポッカリと穴が開いた。長女は結婚して大連に住み、次女は自宅から出て一人で暮らし。ポツンと1人になった孤独感に襲われ、虚しさばかりが募る。
「1人でいるより、こっちへ来たら」。声をかけたのが大連の長女だった。2002年(平成14)11月、千田は3か月の旅行ビザとトランクひとつを持って大連空港に降り立った。娘と孫のいる生活に希望が見え出し、「この街だったら生活できる」。いったん帰国した千田は自宅を人に貸して車を処分し、翌年の春節明けに再び大連を訪れた。
中国語を学ぼうと大連海事大学の留学生となったものの、初めての中国語は手強かった。思い悩んでいた時に励ましてくれたのが大学時代の親友だった。「楽しまなければいかん! 隠居はダメ、何かやれよ」。そこで思い浮かんだのがお店の経営である。ビジネスのベテランだが小売の経験はなく、やってみたい、と密かに思っていた。
さて、何を売るか? 「中国人は贈り物が好き。ならばラッピングのお店を」と2004年(平成16)10月、店員として王静を雇って勝利広場地下にお店オープンさせた。しかし、お客はさっぱり来ない。そこで売り物を増やし、ライターやキーホルダー、お香、琥珀の工芸品も扱った。さらには王静が中国結びの技術を習得して作品を売るようにもなった。王静はすでに千田に欠かせないパートナーになっていた。翌年には長姉ら6人の姉兄が大連を訪れ、千田の大連生活を祝福し、励ましてくれた。千田にとってこれ以上の喜びはなかった。
2006年(平成18)秋には勝利広場から温州城に移転オープンし、水晶や玉の製品、各種アクセサリーも扱いはじめた。お客のほとんどが中国人で、小売業がようやく軌道に乗ってきた。千田はこれまで支えてきてくれた人たちへの感謝を忘れない。両親や兄姉、妻や子どもたち、友人、そしてパートナーの王静。恩を感じながら千田は新たな道を歩み続ける。
コメントをどうぞ
更新日: 2011-10-10
クチコミ数: 0
- アジアン (3)
- カフェ (11)
- スイーツ (1)
- チェーン店 (26)
- フードコート (1)
- ラーメン (13)
- 中華料理 (9)
- 和食・日本料理 (35)
- 居酒屋・バー (13)
- 洋食・西洋料理 (6)
- 焼肉 (3)
- 閉店・移転・終了 (134)
- 韓国料理 (16)
- イベント (8)
- エステ・マッサージ (3)
- カラオケ (3)
- クラブ・ディスコ (2)
- サークル (8)
- ショッピング (35)
- ハイキング (2)
- フィットネスクラブ・スポーツ (7)
- プレイスポット (4)
- 学校・スクール (12)
- 広場・公園 (13)
- 旅行 (15)
- 温泉・スパ (1)
- 観光 (52)
- 閉店・移転・終了 (95)
- 3つ星ホテル以下 (11)
- 4つ星ホテル (14)
- 5つ星ホテル (10)
- ホテル・アパートメント (38)
- マンション・オフィス (37)
- 不動産 (6)
- 乗り物 (7)
- 大連お役立ち情報 (14)
- 生活用品 (7)
- 病院・クリニック (13)
- 閉店・移転・終了 (12)
- 飲料・食品 (8)
- okaさんの食楽人生 (7)
- ニュース (1,118)
- ヒューマンストーリー (34)
- 中国、食のあれこれ (14)
- 巻頭インタビュー (64)
- 恵太太の季節を食す (18)
- 管理栄養士の食コラム (18)
- 旅順 (36)
- 開発区 (30)
- 人民路・港湾広場 (20)
- 森ビル周辺 (18)
- 中山広場周辺 (17)
- 会展中心・星海広場 (17)
- 青泥窪橋 (16)
- 民主広場・経典生活 (14)
- 友好広場 (13)
- 西安路 (10)
- ソフトウェアパーク (9)
- 和平広場 (9)
- 黒石礁 (8)
- 大連駅周辺 (7)
- ハイテクパーク (7)
- オリンピック広場 (7)
- 二七広場 (5)
- 大連空港 (4)
- 三八広場 (3)
- 馬欄広場 (2)
- 保税区 (2)
- 解放路 (1)
- 金石灘 (1)
- 華楽広場 (1)