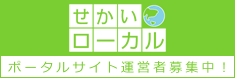- HOME
- » Whenever誌面コンテンツ
- » ヒューマンストーリー
- » 第14話 林 正次 物語
第14話 林 正次 物語

日語教育を通して日中関係に貢献を
大連で見つけた使命と幸せ
日語教育を通して日中関係に貢献を

大連で見つけた使命と幸せ
間もなく大連に来て5年が過ぎようとしている。日本語専門学校「大連志学舎外語培訓学校」の校長を務める林正次は、1年前に中国人の女性と結婚して、すっかりこの地に根を下ろす。日本語教育を通して中国の役に立ちたいと純粋な気持ちで思うし、大連で幸せな家庭を築きたいとも願う。
だが、それまでの林の人生に〝中国〟が入り込む要素はまったくなかった。自ら望んだ進路ではなかったが、ある日突然、縁が生まれたのである。歩んで来た道を振り返る林は、「人生は筋書きのないドラマだ」と、つくづく思う。
仮に人生を80数年とすれば、林は折り返し点に差し掛かった。前半は自然体で周りの流れとともに走って来たが、最近は自分にとって大切なもの、目標といったものが見え始めて来た。これからどんな展開が用意されているのか。林自身も楽しみながらドラマを演じることだろう。
悲しむ余裕もなかった父の突然の死
林は昭和43年(1968)10月、北九州市に生まれた。そのころの日本は高度経済成長の真っただ中で、今の中国の姿と重なり合う発展ぶりだったが、国内外とも大きな出来事が相次いだ。アメリカでは黒人運動指導者のキング牧師やロバート・ケネディ上院議員が暗殺され、ソ連軍がチェコに侵入。国内では学生運動のデモで初めて騒乱罪が適応され、府中の3億円事件も起きるなど、騒然とした世相の中にあった。
だが、林は典型的な戦後の平和な家庭に育った。家族は北九州市で土建業を営む父勇と母愛子、そして1歳上の兄と2歳年下の妹の5人。父は熊本育ちで熊本県立済々黌高校から東京の大学へ進んだが、中退して熊本へ戻り、その後、移り住んだ母と出会って結婚。しかし、周囲に反対され、岐阜まで駆け落ちしたという大恋愛だった。
その父はトラック1台から土建業を始め、好景気もあって一時は50〜60人の従業員を抱えていた。だが、林の記憶にある父は、いつも仕事をしていて、家に帰って来た時には必ず酒を飲んでいた。たまに家にいても酒を飲んでいたが、年に1回は罪滅ぼしなのか、家族旅行に連れて行ってくれた。放任主義で無口な父とやさしい母。そんな安定した家庭は林が中学2年の時に崩れてしまった。父が病死してしまったのである。
林は多感な青春期の年ごろだったが、あまりにも突然の死だっただけに、実感はなく、涙も出なかった。あっと言う間に黄泉の国へと旅立ってしまったのである。「通夜から葬儀はただボーッとしていただけ。いるべき人がいない寂しさを感じたのは1、2か月後だった」。
アルバイトに明け暮れた大学生活
母は姉妹3人でスナックを始め、林は家族の〝縛り〟から解き放たれた。同じ境遇の友人たちと一緒になってやんちゃなこともやった。だが、大好きなサッカーだけは続け、レギュラーのゴールキーパーとして部活動に精を出した。中学から地元の高校へ進学した林は、サッカーではもの足りずにラグビー部へ入部。3年間の部活動では何度もケガをして病院通いが続いた。脱臼は日常茶飯事、鼻骨やあばら骨の骨折も度々だった。しかし、ラグビーでは人間としてのあり方、いさぎよさを身につけた。
「体育会系なので先輩の言うことは絶対的で、服従する精神とともに我慢することを体で覚えた。社会には理不尽なことは山ほどある。しかし、反発するよりとにかくやってみよう、というチャレンジ精神を養ったことは、その後の人生でも大きく役立った」
大学進学は林にとって、初めて悩んだ進路の選択だった。母子家庭だけに経済的な余裕はない。就職して自活の道を選ぶことも考えたが、「無理してでも大学へ行け。苦しいだろうが、大学に入るだけの意味は決して小さくない」とのラグビー部顧問の教師のアドバイスもあり、親類の援助とアルバイトで生活、学費を稼ぐことにして進学を決断した。
大学では商学部に入学したが、勉強は単位を取る程度で生活のほとんどはアルバイトに明け暮れた。福岡市の繁華街・中洲ではバーテンダーとして働いた。当時はバブル経済の絶頂期だっただけに、客のお金の使い方も桁外れである。1晩のチップだけで7、8万円にもなったこともある。このほか、引っ越しセンターや卸売り市場、パチンコ店でもアルバイトをし、家庭教師もやった。
こうして1か月の生活費約15万円は自分で稼ぎ出した。アパートは友人と住み、車も乗り回した。もっとも車検切れ寸前のオンボロ車で、エアコンが壊れていたり、タイヤもよくパンクしたりした。今でもタイヤ交換のスピードが早いのは、このころに培った技のおかげである。
周囲が決めた運命の大連行き
卒業後は銀行に就職。研修期間が終わった後は郡部の支店に配属され、農家を回って集金業務に当たった。スーツ姿にヘルメットをかぶり、単車にまたがる〝行員スタイル〟だ。2年後に東京に転勤となり、約4年間を過ごすことになった。住まいの横浜からの東京までの通勤は、九州育ちの林にとって驚きの連続だった。
ラッシュアワーの混み具合は中途半端ではない。それに通勤電車のコースがいくつもある。九州時代は電車だと、北九州から福岡までの1本だけだが、東京は東海道本線や京浜東北線などがあり、利用する駅も東京や新橋など選択肢は際限なく広がる。「まるでパスルのようだ」と思う。
逆に東京にいて九州人の性格を改めて認識したこともある。東京にも大学時代の同級生が住んでいるが、交差点の反対側で姿を見かけられたときのことである。「オーイ、ハヤシ! きさん、なんしよんか!」。と大声を出して手を振る。周りの人たちは何事か、と視線を向ける。「九州人の性格が東京に来てよく分かった。開放的というか、隠さないというか。方言もそのまんま」。
東京勤務の後は福岡へ戻り、銀行マンとして「可もなく不可もない10年間」が過ぎた。ここで人生の大きな転機を迎えた。銀行マンとして生きるより、自営業の道を選び、退職して福岡で焼肉店を開業。スタート時はまずまずの経営状態だったが、間もなくBSE(牛海綿状脳症)騒動が巻き起こり、大打撃を受けて閉店に追い込まれてしまった。独立の夢はわずか4年で消え失せた。
失意の中で何もすることなく、ただ時間が過ぎる。そんな時、知人を頼って東京へ再びやって来た。銀行の東京勤務時代に知り合った会社社長が、「まだ、若いのに毎日ブラブラしていてはいかん。俺に任せておけ!」と手広く学習塾を経営する理事長を紹介してくれ、「この男を中国で使って欲しい」。林の意向はいっさいおかまいなし。それは決めつけた言い方だった。その理事長とは、志学舎の創立者である水本洋一郎。2005年9月のことである。
水本は当時、サイドビジネスとして大連でエステ店を経営していた。だから「男は必要ない」という水本に、社長は「給料は要らない。仕事は洗濯でも何でもいい」と強引に迫る。結局は「エステで仕事を見つけよう」という水本の言葉を引き出させた。林にとって、縁もゆかりもない中国への旅立ちが決まった瞬間だった。
日系の日本語学校として信頼を集める
エステ店から話は一転。水本の本業である学校を開校させることになり、林に声がかかった。中国人に日本語を教える専門学校で、林は2006年3月29日に大連国際空港へ降り立った。林の担当は前職を生かした経理。しかし、講師陣は少なく、日本人の林が教壇に立つ羽目になってしまった。教えたのは中級クラスの1人だったが、生徒は1か月でやめた。素人の限界と教えることの難しさを思い知らされた。
「教師は経験がすべてだ」。それからは教えることと自らが学ぶ教師修業に明け暮れた。2006年8月から2010年2月まで、朝から夜まで、土、日曜日も教壇に立ち続けた。多いときには50分授業を11コマをもこなして、ひたすら経験を積んだ。そんな林を慕う生徒が増え、対外的な信用も大きくなり、いまでは大連職業大学と提携し、日本語教育を引き受けるまでになった。
会計担当から教師、2007年に教務主任、2008年に副校長、2009年に常務校長、そして2010年12月に校長に就任した林。日系の日本語学校がことごとく撤退する中で、大連志学舎外語培訓学校をコツコツと育て上げて来た。その踏ん張りが実りはじめている。人生の青山を中国に見いだした林はいま、確信を持ってこう言う。
「日中関係は時として微妙なバランスに揺らぐこともある。しかし、大切なのは言葉だ。互いを理解するには言葉が重要になる。私は日本語教育の分野で中国のためになりたい」
個人生活の面でも、中国と切っても切ることのできない縁ができた。2009年12月に1年半にわたって交際した于鳳雲とゴールインした。「結婚して本当によかった」。そんな思いを実感したのは2010年10末だった。急に襲われた心臓の痛み。妻に抱えられて病院に駆けつけ、心筋梗塞と分かり、すぐに入院して手術。1か月後に無事に復帰したが、1人だったらと思うと恐怖感が募る。そのまま死んでいたかもしれない。
家族と一緒に暮らす温かさを知った。そして健康に対する自己管理の足りなさ、次男坊の気楽さも真摯に顧みるようになった。「子どもがいないのは兄妹3人で私だけ。祖母や母にひ孫、孫の顔を見させてやりたい」。林は妻の優しさに包まれた家庭で幸福を噛み締める。
コメントをどうぞ
更新日: 2011-10-10
クチコミ数: 0
- アジアン (3)
- カフェ (11)
- スイーツ (1)
- チェーン店 (26)
- フードコート (1)
- ラーメン (13)
- 中華料理 (9)
- 和食・日本料理 (35)
- 居酒屋・バー (13)
- 洋食・西洋料理 (6)
- 焼肉 (3)
- 閉店・移転・終了 (134)
- 韓国料理 (16)
- イベント (8)
- エステ・マッサージ (3)
- カラオケ (3)
- クラブ・ディスコ (2)
- サークル (8)
- ショッピング (35)
- ハイキング (2)
- フィットネスクラブ・スポーツ (7)
- プレイスポット (4)
- 学校・スクール (12)
- 広場・公園 (13)
- 旅行 (15)
- 温泉・スパ (1)
- 観光 (52)
- 閉店・移転・終了 (95)
- 3つ星ホテル以下 (11)
- 4つ星ホテル (14)
- 5つ星ホテル (10)
- ホテル・アパートメント (38)
- マンション・オフィス (37)
- 不動産 (6)
- 乗り物 (7)
- 大連お役立ち情報 (14)
- 生活用品 (7)
- 病院・クリニック (13)
- 閉店・移転・終了 (12)
- 飲料・食品 (8)
- okaさんの食楽人生 (7)
- ニュース (1,118)
- ヒューマンストーリー (34)
- 中国、食のあれこれ (14)
- 巻頭インタビュー (64)
- 恵太太の季節を食す (18)
- 管理栄養士の食コラム (18)
- 旅順 (36)
- 開発区 (30)
- 人民路・港湾広場 (20)
- 森ビル周辺 (18)
- 中山広場周辺 (17)
- 会展中心・星海広場 (17)
- 青泥窪橋 (16)
- 民主広場・経典生活 (14)
- 友好広場 (13)
- 西安路 (10)
- ソフトウェアパーク (9)
- 和平広場 (9)
- 黒石礁 (8)
- 大連駅周辺 (7)
- ハイテクパーク (7)
- オリンピック広場 (7)
- 二七広場 (5)
- 大連空港 (4)
- 三八広場 (3)
- 馬欄広場 (2)
- 保税区 (2)
- 解放路 (1)
- 金石灘 (1)
- 華楽広場 (1)